
喪主・関係者の知識




家族や近親者のみで行われる「家族葬」。
一般葬よりも小規模のため、「喪主は必要なの?」と悩む人もいるのではないでしょうか?
結論から申しますと家族葬でも喪主は必要です。
ただし一般葬と比較して簡易的になるケースもあります。
今回は家族葬における喪主の役割について解説します。
この記事を読んでわかることは以下の4つです。
喪主になる優先順位は①配偶者、②長男・長女(家を継ぐ者)となり、一般葬と変わりありません。
故人に配偶者がいない場合は兄弟姉妹の年長者が喪主を務めるのが一般的。
ただし故人が遺言書で指名している場合はその方が優先的に喪主となります。
故人の血縁者がいないケースなら友人や知人、施設に入っていれば施設長が喪主を務めることが多いでしょう。
この場合「喪主」とは呼ばず、「友人代表」や「世話人代表」といった呼び方になります。
ちなみに「施主」とは葬儀の費用を出す人を指し、「喪主」は葬儀全般を取り仕切る人となります。
しかし最近は喪主が施主を兼ねていることが多いですね。
家族葬での喪主の仕事を大まかに「葬儀前」・「通夜・葬儀」・「葬儀後」と3つに分けて解説していきます。
まずは「葬儀前」、つまり故人の危篤~ご遺体の安置までに喪主がやるべきことを説明します。
故人が危篤の際、電話などで親族へ連絡して知らせる必要があります。
連絡するのは主に3親等くらいまでの親族が一般的でしょう。
危篤時は早朝・深夜問わず連絡しても構いません。
すでに亡くなってしまった場合は、例えば深夜であれば朝になってから知らせるなどしましょう。
https://with-house.jp/wp/blog/2023/07/15149/
故人の臨終後にやるべきことは、死亡診断書の受け取りや葬儀社の決定、遺体の安置場所の確保などです。
故人の臨終後、医師から「死亡診断書」を受け取ります。
死亡診断書は7日以内に市区町村役場へ提出してください。
提出すると埋火葬許可証(地域によって名称は異なります)が発行されます。
火葬時や納骨時に必要な書類となりますので、そちらも大切に保管してください。
葬儀社がすでに決まっている場合は速やかに連絡しましょう。
ご遺体の安置場所についても相談に乗ってくれますし、これからやるべきことも指南してくれます。
喪主の務めは何回も経験することではないため、わからないことも多いでしょう。
葬儀のプロに任せておけば抜かりなく、安心して準備を進めていけます。
ご遺体の安置場所は葬儀社や自宅が一般的ですが、自宅の場合は布団の用意が必要です。
ご遺体を移動した後は北枕(または西)にして安置し、必要であれば枕経をあげてもらいます。
ご遺体を安置できたら葬儀へ向けての準備が始まります。
通夜・葬儀の日程調整や菩提寺への連絡、葬儀プランなどを決めましょう。
通夜・葬儀日を決める際は、まず火葬場のスケジュールをチェックしてください。
火葬できる日を決めてから通夜・葬儀の日程を逆算して決めていくのがスムーズです。
友引の日は火葬に不向きであるという風習を考慮して、友引を休みとしている火葬場もありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
菩提寺がある場合は僧侶の予定も確認しましょう。
菩提寺はないけれど、葬儀ではお経をあげてもらいたいという方は、葬儀社等が行なっている「寺院紹介」を利用すると便利ですよ。
家族葬のウィズハウスでも寺院紹介を承っております。
お布施の金額なども明瞭でわかりやすいと評判ですので、よろしければご相談ください。
https://with-house.jp/wp/temple/
葬儀の日程が決定したら参列者を決めていきます。
家族葬では「○親等までは必ず呼ぶ」といった明確なルールがありません。
参列者を自由に選べる反面、悩んでしまうこともあるでしょう。
一般的には2親等まで呼ぶ喪家が多いようですが、同居家族のみで行うケースもあります。
参列する人数によって式場の広さも変わってきますので、親族との関係や費用との兼ね合いなども考慮しながら決定しましょう。
親族に相談もなく通夜や葬儀を執り行ったことでトラブルに発展するケースもあります。
参列者の選定は親族や葬儀社に相談しながら慎重に進めてください。
参列者が決まった後、必要であれば案内状を作成します。
家族葬の場合、このタイミングで参列者以外に訃報のお知らせを送らないよう気を付けてください。
参列しない方へは葬儀後に訃報をお知らせする手紙をお送りします。
故人と親しかった友人など、どうしても知らせたい方がいる場合は連絡してもかまいません。
その際に家族葬であること、参列不要であることをしっかりと伝えましょう。
家族葬では香典の受付や香典返しの手間を省くため、香典を辞退する喪家もいらっしゃいます。
ただし家族葬といっても僧侶へのお布施や一連の葬儀費用は必要ですので、よく考えて香典を辞退するかどうか決定しましょう。
もし香典を辞退する場合は、案内状や電話で伝えておくと相手方も困りません。
会社関係にも同様に家族葬であることを伝えておいてください。

通夜・葬儀における喪主の主な仕事として「開式前の準備」・「弔問客と僧侶への対応」・「挨拶」があります。
喪主が行う仕事について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
通夜の日に喪主がやるべきことは、納棺と開式前の準備、それから弔問客への対応と挨拶です。
喪主・遺族は通夜が始まる2~3時間前に納棺を行います。
納棺は葬儀社の方が色々と指示してくれますので従いましょう。
このとき故人は死に装束をまといます。
ただし、納棺は通夜当日に行うと決まっているわけではないので、通夜前日や前々日に行う場合もあります。
通夜が始まる前に弔電や供花の並び順のチェック、通夜式の進行の確認などもしておきましょう。
供花は故人と親しい人を中央として左右に広がっていく形となります。
参列者に失礼のないよう、しっかり確認しましょう。
通夜における喪主の仕事で最も大切なのが弔問客への対応です。
お悔やみの言葉を述べられたらお礼を伝えてください。
- 弔問客への挨拶例文
- 本日はご多用中のところありがとうございます。
- 生前は○○がお世話になりました。
また僧侶の出迎えと挨拶、お布施をお渡しするのも喪主の役目です。
僧侶への挨拶は以下のような文言を述べるといいでしょう。
- 僧侶への挨拶例文
- 本日はご足労いただき、誠にありがとうございました。
- 予定通り○時より通夜式を開始させていただきますので、宜しくお願いいたします。
通夜式で喪主が挨拶するタイミングは、「通夜終了時」と「通夜振る舞いの開始前後(用意する場合)」の2回です。
通夜終了時の挨拶では、参列者へのお礼と翌日の告別式の告知、通夜振る舞いの案内を伝えましょう。
通夜終了時の挨拶例文も参考になさってください。
- 通夜終了時の挨拶例文
- 本日は亡き○○の通夜式にご参列賜りまして、誠にありがとうございます。
- ○○もさぞ喜んでいることと思います。
- 生前は皆様からひとかたならぬご厚誼を預かり、深く感謝しております。
- 我々遺族にも、故人の生前同様変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。
- 明日の葬儀は○○会場で○時より執り行う予定となっております。
- 何卒宜しくお願い申し上げます。
- なお、ささやかではございますがお食事の席をご用意しております。
- 故人を偲びながらお召し上がりいただければと思います。
- (通夜振る舞いがない場合:本来であればお食事をご用意すべきところですが、都合によりお席がご用意できておりません。何卒ご了承ください。改めまして本日はありがとうございました。どうぞお気を付けてお帰りください)
通夜振る舞いの開始時・終了時の挨拶例文は以下のようになります。
- 通夜振る舞い開始時の挨拶例文
- 皆さま、本日はありがとうございました。
- ささやかではございますがお食事をご用意しました。
- 故人の思い出話などされながら、お時間の許す限りゆっくりとおくつろぎください
- 通夜振る舞い終了時の挨拶例文
- 本日はお忙しい中、○○の通夜式にご参列いただき誠にありがとうございました。
- お話はなかなか尽きませんが、そろそろ時間が参りましたのでこのあたりで終了させていただきたく存じます。
- 明日の葬儀は○○会場で○時より執り行いますので、何卒宜しくお願いいたします。
- どうぞお気を付けてお帰りください。
葬儀・告別式も通夜式とやることは同様です。
開式前の準備と弔問客・僧侶への対応、そして挨拶を行います。
告別式前の準備
喪主は告別式の始まる数時間前に式場へ入ります。
会葬礼状や返礼品の確認、火葬場への同行人数やバスなどもチェック。
精進落としの数などもしっかりと確認しておきましょう。
僧侶の出迎えと挨拶
告別式でも弔問客の対応と僧侶の出迎えは喪主の大切な仕事です。
通夜式の例文を参考にご対応ください。
告別式での挨拶
告別式での喪主の挨拶は、「出棺時」と「精進落としの開始前後」の2回です。
ごく小規模な家族葬であれば、かしこまりすぎた挨拶にしなくても良いでしょう。
しかし親族なども呼ぶ場合は最低限の礼節に沿った挨拶が必要です。
出棺前の挨拶の例文は以下の通りです。
- 出棺前の喪主挨拶例文
- 本日はご多用中のところ、○○のためにご会葬くださいまして誠にありがとうございました。
- ○○も生前特にお世話になった皆様にお集まりいただき、さぞ喜んでいることと思います。
- 生前のご厚誼に対し厚く御礼申し上げます。
- 今後とも故人の生前同様、残された私どもにもご指導・ご厚誼賜りますようお願い申し上げます。
- 本日は誠にありがとうございました。
精進落としの開始時・終了時の挨拶の例文もご紹介します。
- 精進落とし開始時の挨拶例文
- 本日はご多用中のところ、○○のためにお集まりいただきありがとうございました。
- おかげさまでつつがなく葬儀を終えることができました。
- 誠にささやかではございますが、皆様への感謝を込めましてお食事の席をご用意させていただきました。
- 故人の思い出話などをお話ししながら、時間の許す限りゆっくりとおくつろぎください。
- 本日はありがとうございました。
- 精進落とし終了時の挨拶例文
- 皆さま、本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございました。
- 私どもの知らない故人のエピソードなども知ることができ、大変貴重な時間を過ごすことができました。
- もっとお話をお聞きしたいところですが、このあたりでお開きとさせていただきたいと存じます。
- あらためまして本日はありがとうございました。
- どうぞ足元にお気をつけてお帰りください。
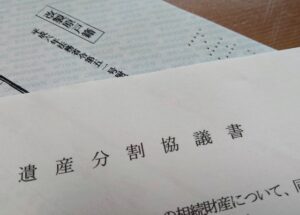
通夜・葬儀より大変だといわれているのが「葬儀後の諸手続き」です。
主な手続きには以下のようなものがあります。
喪主が中心となってこれらの手続きをこなしていかなければなりません。
兄弟など親族がいる場合は無理せず、上手に役割分担をして喪主だけに負担がかからないようにしましょう。
葬儀後の手続きについては以下の記事でも詳しくお伝えしています。
https://with-house.jp/wp/blog/2023/12/16176/
ごく身内で行う家族葬であっても、喪服の着用はマナーです。
昔は喪主というと「正喪服」の着用が一般的でしたが、最近は「準喪服」の着用が増えていますね。
「正喪服」とは男性なら紋付羽織袴やモーニング、女性ならブラックフォーマルを指します。
「準喪服」は男性ならブラックスーツ、女性なら黒のワンピースやアンサンブルになります。
小物も黒で統一しますが、光沢のある生地やアクセサリーなど華美になるものは身につけません。
家族葬に参列する際の服装については以下の記事も参考になさってください。
https://with-house.jp/wp/blog/2017/06/4641/
お葬式についてよくわかる
お葬式ガイドブックや各施設の紹介している
パンフレット、具体的な葬儀の流れがわかる資料など
備えておけば安心の資料をお送りいたします。
