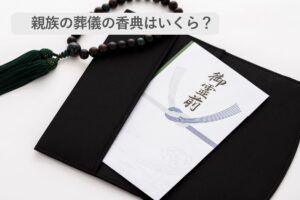
葬儀の知識




初めて喪主を務める方にとって、葬儀や火葬の場での「挨拶」は悩ましいものです。
特に火葬は出席する機会自体が少ないため、何を話せばよいのか想像もつかないという方も多いようです。
しかし、あらかじめ挨拶のタイミングや内容を知っておけば、落ち着いて気持ちを伝えることができます。
この記事では、火葬において喪主が挨拶をするタイミングをご紹介するとともに、それぞれの場面での例文やポイントを詳しくご紹介します。
<火葬の際に喪主が挨拶をするタイミング>
ご遺族としての大切な時間に、無理なく気持ちを届けられるよう、ぜひ参考にしてみてください。

火葬に関する場面で喪主の挨拶が求められることが多いのは、以下の3つのタイミングです。
葬儀が終わり、棺を霊柩車に乗せて火葬場へと向かう「出棺」のタイミングでは、喪主や遺族代表が参列者に向けて一言挨拶をすることがあります。
この挨拶では、ここまで無事に式を終えられたことへの感謝の気持ちと、ここでお別れとなる方々への配慮を込めた内容が一般的です。
規模の大きな葬儀ではマイクを使うこともありますが、小規模な葬儀であれば、ごく親しい方々に向けて簡単に言葉を添えるだけでも構いません。
火葬場に到着すると、火葬炉の前で「納めの式」(最後のお別れの儀式)が行われます。
この儀式が終わり、参列者が焼香を済ませた後に喪主が挨拶を求められることがあります。
納めの式の挨拶は、故人との最後のお別れに付き添ってくださった方々への感謝や、これから収骨までの待機時間についての案内を含めると丁寧です。
気持ちが高ぶってしまい、言葉が出てこないような場合、無理をする必要はありません。短く、心のこもった一言で十分です。
火葬が終わった後、親族や参列者とともに「精進落とし」の食事をいただく場合には、その開始時と終了時にも喪主からの挨拶が行われることが一般的です。
火葬が終わるのを待つ間に精進落としを行う地域もあり、その場合も挨拶を行うケースがあります。
開始時には、改めて参列してくれたことへの感謝と、ささやかな席であることの説明を。
終了時には、長時間にわたるお付き合いへのお礼や、今後の法要の案内などを伝えるとスムーズです。
食事の場は比較的和やかな雰囲気になりやすいので、形式ばらず、自然体で話すことを意識するとよいでしょう。

出棺時の挨拶は、ご遺体が霊柩車に乗せられ、火葬場へ向かう前に、参列してくださった方々へ感謝の言葉を伝えるのが一般的です。
特に葬儀・告別式に多くの方が参列した場合は、全体を締めくくる意味でもこの挨拶が重要になります。
「本日はご多用の中、父○○のためにご会葬いただきまして、誠にありがとうございました。おかげさまで、無事に通夜・葬儀を執り行うことができました。
父には長年患っていた持病がありましたが、病気とつきあいながらも、趣味の写真や孫との交流を楽しんでいました。今年に入り病状が悪化、入院加療しておりましたが、〇月〇日〇時〇分、私たち家族に見守られる中、息を引き取りました。
生前故人が賜りましたご厚情に対し、深く感謝申し上げますとともに、遺された家族に対しても、変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。
本日は厳しい暑さの中、お見送りいただきありがとうございました。ご同行くださる皆さまには、どうぞお気をつけてご移動くださいますようお願い申し上げます。」
「本日はお忙しい中、父○○のためにお集まりいただき、本当にありがとうございました。これから火葬場へと向かいますので、ご一緒くださる方はどうぞよろしくお願いいたします。短い時間ではありますが、最後まで見送っていただけること、家族一同ありがたく思っております。」

火葬場に到着すると、棺を火葬炉に納める前に「納めの式」と呼ばれる最後のお別れの儀が行われます。
僧侶が同行する場合は読経していただき、参列者は順にお焼香を行います。
焼香が終わった後、喪主が一言挨拶をする場合があります。
「皆さま、本日はお忙しい中、故人のお見送りをいただき、誠にありがとうございました。これにて納めの式を終え、火葬に入らせていただきます。このあと、収骨まで控室でお待ちいただくことになります。最後までどうぞよろしくお願いいたします。」
「本日は、最後まで見送ってくださり、本当にありがとうございます。…(一呼吸おいて)控室の方へご案内いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。」
火葬を終え、収骨を済ませたあとに行われる「精進落とし」は、参列者へのねぎらいと感謝を伝える場でもあります。
火葬という大切な儀式を終え、故人を偲びながら食事を共にすることで、遺族と参列者の心も区切りを迎える場面です。
喪主は、この精進落としの開始と終了時に簡単な挨拶を求められることが一般的です。
「本日は、父○○のために最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。ささやかではございますが、お食事をご用意いたしましたので、どうぞ召し上がってください。故人を偲びながら、ゆっくりお過ごしいただけましたら幸いです。」
「本日は朝早くから長時間にわたり、最後まで故人をお見送りいただき、本当にありがとうございました。今後の法要などにつきましては、改めてご案内させていただきます。本日はお足元の悪い中、誠にありがとうございました。どうぞお気をつけてお帰りください。」

火葬前後に喪主として挨拶する際は、「何を言えばいいんだろう」「間違ったらどうしよう」と、多くの方が不安になります。
ただ、必要なのは「完璧な言葉」よりも「感謝の気持ち」であり、大切な家族とのお別れに参加してくれた皆様に、気持ちをを伝えることができれば、それで十分といえるのではないでしょうか。
たとえ言葉に詰まってしまっても、震える声であっても、それは「心からの想い」が伝わる瞬間です。
難しい表現や形式にとらわれすぎず、「来てくれてありがとう」「見送ってくれてありがとう」という気持ちを、そのまま言葉にするだけで、伝わるものがあると思います。
もし、気持ちが高ぶって声を出すのが難しければ、無理に挨拶しなくても構いません。
代わりに家族の方にお願いしてもいいですし、あらかじめ紙に書いておくという方法もあります。
大切なのは、「しっかり挨拶しなきゃ」と自分にプレッシャーをかけすぎず、できる範囲で、できる形で想いを届けること。
多くの場合、葬儀や火葬の場は、気持ちの整理がつかない中で迎えることになります。
そのなかで、精一杯の挨拶をすることは、供養のひとつの形ともいえるでしょう。
A.必ず挨拶をしなければいけないわけではありませんが、参列者への感謝を伝える場として求められることがあります。無理に話す必要はありませんが、一言でも「ありがとうございます」と伝えられると丁寧な印象になります。
A.文章を暗記しようとせず、「伝えたい気持ち」を自分の言葉で話すと、自然と伝わります。心配な場合はメモを用意しても問題ありません。背伸びせず、できる範囲で話すことを心がけると、緊張が和らぎます。
A.一般的には出棺時、火葬場での納めの式後、精進落としの際など、それぞれの場面で簡単な挨拶があると丁寧な印象になります。ただし、葬儀の規模や地域によって省略されることもあります。
A.はい、大丈夫です。四十九日法要などの予定が決まっていれば、簡単にお知らせすると親切です。詳細は後日改めて連絡する旨を添えましょう。
A.少人数の家族葬では、改まった挨拶をしないケースも多くあります。親族との関係性にもよりますが、「今日はありがとう」と声をかけるだけ十分な場合もあります。
火葬という場面は、人生のなかでも特に心が揺れる時間です。
喪主として、突然挨拶を求められることに戸惑う方も多いと思います。
今回ご紹介したように、挨拶が必要になる主なタイミングは以下の3つです。
それぞれの場面にはふさわしい言葉や伝え方がありますが、何より大切なのは「感謝の気持ちを、できる形で伝える」こと。
立派な挨拶である必要はなく、短くても、つたなくても、心を込めた言葉はしっかり届くでしょう。
コープの家族葬ウィズハウスでは、火葬に関する情報を多数発信しています。
「火葬がはじめてで何もわからない」「火葬について一通り知りたい」といった場合、下記のブログをご参照いただくか、お電話やメールで、お気軽にご相談ください。
【関連記事】
火葬の流れを徹底解説|出棺から収骨まで7つの手順と所要時間
お葬式についてよくわかる
お葬式ガイドブックや各施設の紹介している
パンフレット、具体的な葬儀の流れがわかる資料など
備えておけば安心の資料をお送りいたします。
