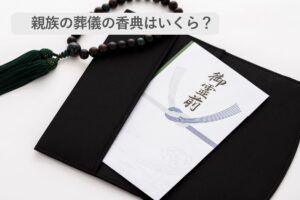
葬儀の知識




火葬にかかる時間ってどれくらい?
火葬中の待ち時間はどう過ごせばいいの?
死亡から24時間以内に火葬できないって本当?
これから葬儀を行う可能性がある方は、火葬の「時間」に関するさまざまな疑問を抱えているのではないでしょうか。
筆者は過去3年間で3人の身内を亡くし、短期間に3度、身内の火葬を経験しました。
その経験をもとに本記事では、火葬にかかる時間の目安や法律による制限、火葬場の営業時間帯、待ち時間の過ごし方など、実際の流れに沿って分かりやすく解説します。
目次
火葬にかかる時間は、一般的に60〜120分程度が目安とされています。
ただし、遺体の状態や火葬場の設備、季節などによって多少前後することもあります。
ここでは、火葬に必要な時間の具体的な目安や、火葬炉の仕組み、温度との関係について詳しく見ていきましょう。
火葬に必要な時間は、多くの場合1時間〜2時間程度です。
これは、火葬炉に遺体を納めてから、収骨ができる状態になるまでの目安となります。
ただし、以下のような要因で時間が変わることもあります。
また、子どもや乳児の場合は30〜50分程度で終了することもあります。
火葬は、火葬炉の中を高温に保ちながら行われます。一般的に、
この温度設定がされている理由は以下の通りです。
ただし、温度が高ければ高いほど良いというわけではありません。遺骨をきれいに残すためには、適切な火力と時間が必要です。火葬時間が短すぎると骨が脆くなり、逆に長すぎると骨が炭化してしまうため、火葬は細かな温度調整をしながら丁寧に行われています。
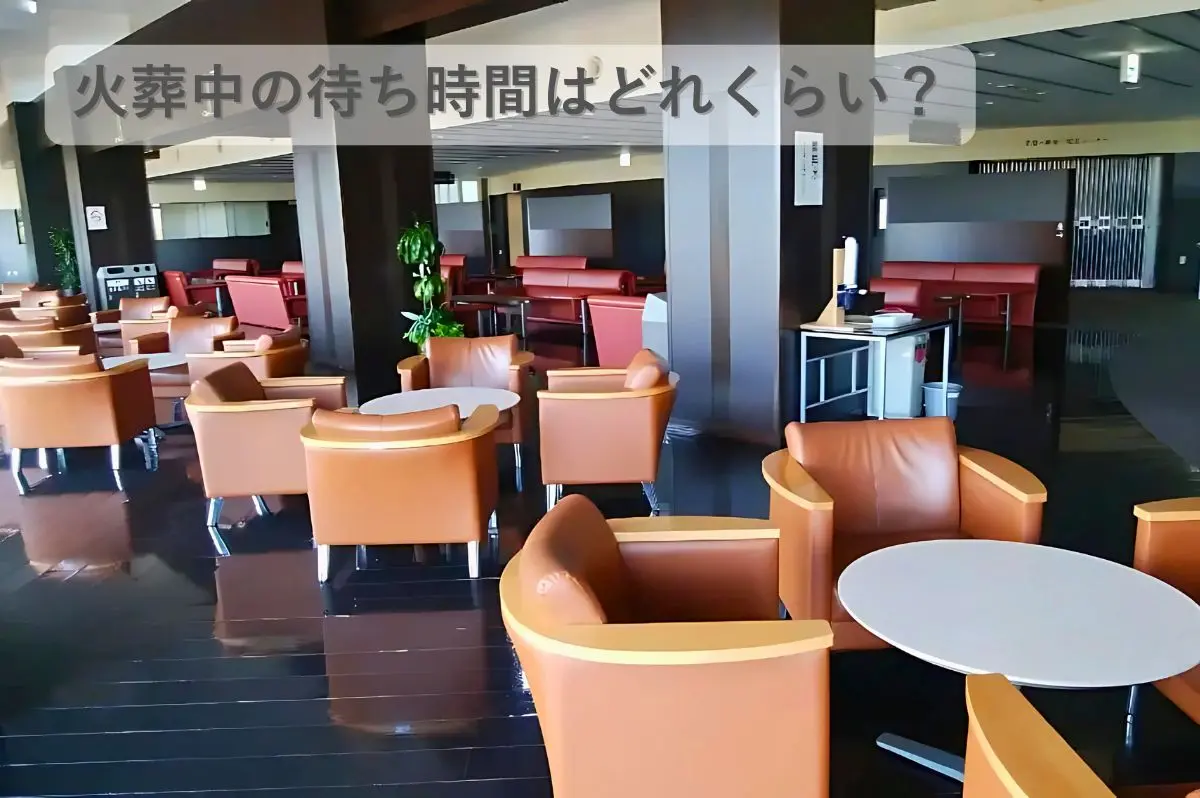
火葬中の待ち時間は、遺族や参列者にとって静かに過ごす時間でもあります。
しかし、「何をして過ごせばいいの?」「お菓子や食事を出すべき?」と悩む方も少なくありません。
この章では、火葬中の待機時間の目安や、控室での過ごし方、飲食マナーなどを分かりやすくご紹介します。
火葬の所要時間は先述のとおり60〜120分程度。時間に開きがあるのは、火葬炉の種類や冷却装置の有無が関係しています。
火葬の間、遺族や親族は火葬場の控室やロビーで待機するのが一般的です。
控室やロビーの利用方法も施設によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
例えば、札幌市の2か所の火葬場(里塚斎場・山口斎場)には、無料で利用できるロビーと利用料が必要となる控室が用意されています。
控室にはテーブルや椅子、給湯設備などが備えられていることが多く、次のような過ごし方が一般的です。
札幌市の火葬場について詳しく知りたい方は、下記のブログをご覧ください。
【関連記事】札幌市山口斎場のアクセスや施設の特徴、利用料について
【関連記事】札幌市里塚斎場のアクセスや施設の特徴、利用料について
火葬中の控室では、お菓子や軽食を提供することもよくあります。
これは地域の風習や家族の判断によるところが大きいのですが、特に午前中の火葬であれば、おにぎり・お茶・まんじゅうなどを用意して、簡単な飲食をしながら待つことがあります。
中でもよく用意されるのは次のような飲食物です。
紙皿や紙コップなどの使い捨て食器も準備しておくと便利です。
また、葬儀社に依頼して、待ち時間に仕出し弁当を食べることが通例となっている地域もあります。
待ち時間に食事をとるかどうかについては、地域の葬儀事情に詳しい葬儀社に確認することをおすすめします。
コープの家族葬ウィズハウスでは、北海道全域の火葬についてのご相談もお受けしていますので、気になることがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。
控室やロビーは、故人を見送った直後の静かな時間を過ごす場所です。
そのため、飲食の際も以下のようなマナーに気を配りましょう。
また、スマートフォンの使用は必要最低限にとどめ、通話をする場合は一度席を外すなどの配慮をすると、他の参列者も気持ちよく過ごせます。

私が過去3年で遺族として経験した葬儀は、いずれも小規模な家族葬でした。
| 故人 | 参列者数 | 火葬場同行人数 |
|---|---|---|
| 実父 | 7名 | 7名 |
| 祖母 | 7名 | 7名 |
| 義父 | 15名程度 | 10名程度 |
実父と祖母の葬儀の際は、少人数だったことと、じっとしていられない子どもを連れていたことから、控室は利用しませんでした。
火葬を待つ間、最初は大人も子どももロビーで過ごし、お菓子をつまみながら父の思い出話などをしていました。
やがて、予想通りじっとしていられなくなった子どもたちを連れてテラスへと移動し、子どもたちの相手をしていたことをよく覚えています。本章上部の画像は、その時に撮ったテラスの写真です。
最高気温30度を超える快晴だったため他に人がおらず、日差しは厳しかったものの、時々日陰に入って暑さをしのぎながら、気兼ねなく過ごすことができて助かりました。
子連れで火葬場を利用する際は、このようなテラスや中庭、キッズルームなど、子どもと一緒に過ごしやすい空間があるかどうかを確認しておくことをおすすめします。
実父と祖母の火葬は札幌市で行いましたが、札幌市では火葬中に食事をとるケースが多く、仕出し弁当等を用意するご家庭も珍しくありません。
ただし、私たちはごく身内のみで葬儀を行ったため、火葬中には食事をとらず、火葬が終わってから火葬場を出て食事をとりました。
実父と祖母が立て続けに亡くなった1年半後に、北海道滝川市で義父の葬儀を行いました。
滝川市でも火葬中に食事をすることが通例となっており、10名程度が同行したため、控室と仕出し弁当を用意して、食事をしながら家族や親戚と会話をしていました。
この時は葬儀開始が9時、火葬開始が10時半過ぎだったため、あまりお腹は空いていませんでしたが、食事をしたことで、待ち時間の長さはあまり気になりませんでした。
このように、火葬を待つ間は、故人の思い出話をしながら、控室やロビーで食事をとったりお菓子をつまんだりするのが、一般的な過ごし方といえるでしょう。
日本では法律により、死亡後24時間以内の火葬が禁止されています。
宗教儀礼やセレモニーを行わない「火葬式」や「直葬」と呼ばれる葬儀形式であれば、火葬までの時間を短縮することができるのではないかと思う人もいるかもしれません。しかし、この法律により、逝去後24時間以上はご遺体を安置する必要があります。
これは衛生面や誤認防止の観点から設けられた大切なルールです。
ここでは、この「24時間ルール」の意味や背景、例外となるケースについて詳しく解説します。
日本では、死亡後24時間を経過しなければ火葬してはならないという決まりが、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)で定められています。
出典:厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律」
これは、誤って生きている人を火葬してしまうような事故を防ぐために、昔から設けられている法律です。
現代のように医療が発達していなかった時代は、死亡判定が難しかったため、仮死状態にある人を「死亡した」と判断してしまうことがあったようです。
また、医療が発達した現代でも、救急隊員が、生きている人を誤って死亡判断したという事例があります。
このように、死後24時間以上経過しなければ火葬できないという法律は、万が一の蘇生の可能性に備えるためにも、必要といえるでしょう。
ただし、「感染症など、衛生上の理由による火葬」の場合、例外的に24時間以内の火葬が認められるケースがあります。
たとえば、エボラ出血熱やペストのような一類感染症に該当する場合、自治体の許可があれば24時間を待たずに火葬されることがあります。
このようなケースでは、感染拡大を防ぐことが最優先とされるため、速やかな火葬が行われます。
また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が流行し始めた当初も、感染リスクへの懸念から、できる限り速やかな火葬が推奨されました。
当時は、ご遺体との面会や通夜・葬儀の機会が制限されることも多く、通常の火葬スケジュールとは異なる対応が求められました。

現在では、火葬がごく当たり前のように行われていますが、なぜ日本では火葬が主流になったのでしょうか?
実は、日本でもかつては土葬が一般的で、火葬が本格的に広まったのは明治時代以降のことです。
仏教が伝来した古代から中世にかけて、日本では土葬と火葬が混在していましたが、江戸時代までは多くの地域で土葬が主流でした。
特に地方では「遺体は土に還すもの」という考えが根強く、山や寺の境内に埋葬する習慣が残っていたのです。
火葬が一般化した背景には、以下のような理由があります。
・都市部での土地不足と人口増加
・伝染病予防など衛生面への配慮
・火葬技術と設備の発展
・法律による制度整備(墓埋法など)
とくに都市部では「土葬できる土地がない」「臭いや感染症のリスクがある」といった問題が深刻化してきたため、火葬が推奨されるようになりました。
厚生労働省の統計によると、2022年度の火葬率は99.97%に達しています。
約162万8,000件の葬送のうち、火葬されたのは約162万7,500件という高い数値です。
残りの0.03%は、ごく少数の胎児などが対象であり、成人の土葬はほとんど行われていません。
このように、日本で火葬が主流となったのは、文化・衛生・法制度・技術の進歩が重なった結果といえるでしょう。
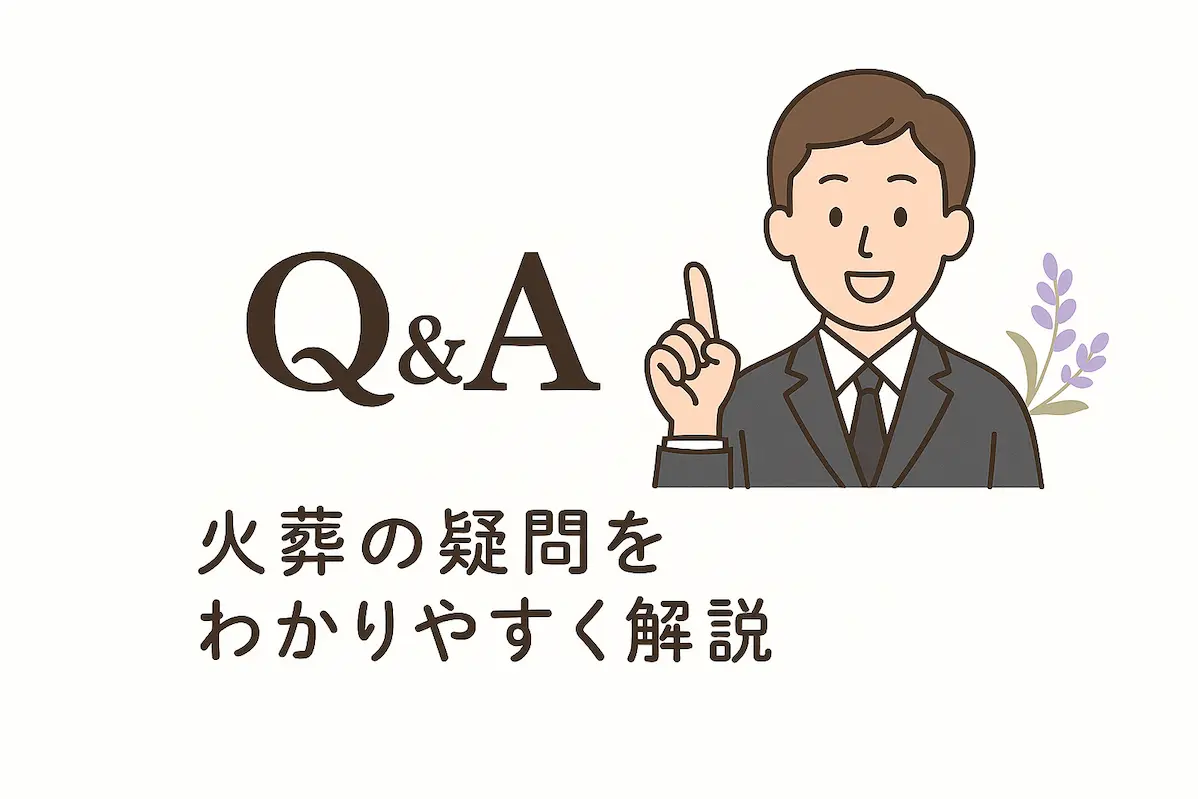
火葬について調べる中で、ふと湧いてくる「ちょっとした疑問」。
ここでは、火葬の時間・服装・マナーなどにまつわるよくある質問を、Q&A形式でまとめました。
A. はい、一般的に60〜120分かかるのが普通です。
体格や火葬場の設備、季節によって火葬時間は異なります。待ち時間は少し長めに見積もっておくと安心です。
A. 基本的には黒の喪服が正式ですが、家族葬や直葬など小規模な葬儀では、黒や濃紺の平服で参列することもあります。
地域や宗教による違いもあるため、迷ったときは親戚や葬儀社に相談すると安心です。
A. 火葬式は、通夜や告別式を行わず、火葬のみを執り行う葬儀形式です。
費用を抑えられるというメリットがありますが、お別れの時間が短くなるため、事前に家族や親族の理解を得ておくことが大切です。
A. 副葬品の持ち込みは火葬場によってルールが異なります。
燃えにくいもの・金属・ビニール製品などは基本的に入れられません。
棺に納める前に、必ず葬儀社や火葬場に確認しましょう。
A. 昔は土葬が主流で、火葬は徐々に普及しました。
また、古い火葬炉に比べて最新の火葬炉は性能が上がり、効率的かつ衛生的に火葬できるようになりました。
冷却設備が備えられている施設も増えたため、昔に比べて待ち時間は短縮傾向です。
法律の整備や社会の意識変化も大きな違いのひとつです。
火葬にかかる時間は、一般的に60〜120分程度です。
火葬中は控室で静かに過ごす時間となり、軽食やお菓子を用意して親族と語らうこともあります。
死亡から24時間以内の火葬は法律で禁止されていることや、火葬場の混雑状況によって希望する時間帯が取れないこともある点は覚えておきましょう。
葬儀は、悲しみの中にも慌ただしさのあるもの。
だからこそ、火葬の時間や流れを事前に把握しておくことで、当日スムーズに行動でき、故人とのお別れの時間を心残りなく、大切に過ごすことができます。
コープの家族葬ウィズハウスでは、北海道全域の火葬に関するご相談を受け付けています。
火葬に限らず、葬儀や葬儀前後のご相談・ご不安があれば、どうぞお気軽にご連絡ください。
お葬式についてよくわかる
お葬式ガイドブックや各施設の紹介している
パンフレット、具体的な葬儀の流れがわかる資料など
備えておけば安心の資料をお送りいたします。
