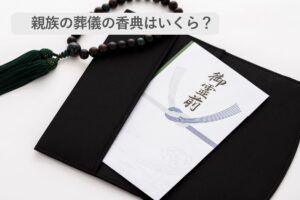
葬儀の知識



こんにちは、家族葬のウィズハウス スタッフの大崎です。
仏教の中にはさまざまな宗派があり、宗派ごとにお葬式の儀礼や作法、マナーも異なります。
今回は仏式宗派の一つである「浄土真宗」についてのお話。
日本で最もたくさんの信者を抱える宗派の一つである浄土真宗の教えや特徴、葬儀の流れ、マナーをご紹介します。

浄土真宗は鎌倉時代の僧侶、親鸞聖人(しんらんしょうにん)によって開かれた仏教宗派。
親鸞聖人は、浄土宗を説く法然上人(ほうねんじょうにん)の弟子でした。
親鸞聖人は、浄土宗の「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)を唱えるだけで阿弥陀如来(あみだにょらい)からの救いを得られ、極楽浄土へ行ける」という他力本願の教えをさらに強めた「絶対他力」の教えを説き、浄土真宗を開いたのです。
絶対他力とは「念仏を唱えなくても浄土真宗を信じるだけで誰でも仏の救いを得ることができる」という教え。
本来、仏教の教えとは厳しい戒律を守り読経や瞑想などの修行の末、悟りを開き手に入れるものでした。
それが浄土真宗では難しい戒律や修行を行わず、浄土真宗を信じるだけで救いを得られるということで、室町時代には庶民を中心に広く信仰されるようになりました。
現在でも、日本の仏教宗派で一番多くのお寺と信徒を抱える宗派です。
また、浄土真宗には「冥土」という概念がなく、亡くなった方はすぐに極楽浄土へ成仏することができる「臨終即往生」という教えもあります。
そのため葬儀では、授戒や引導、追善供養の回向(えこう)といった故人の魂が成仏するための儀式はありません。
浄土真宗の葬儀は、仏へ感謝を伝え、残された者たちが故人を偲ぶための儀式となります。
浄土真宗は大きく分けて「浄土真宗本願寺派」と「真宗大谷派」の二つに分かれます。
二つの宗派とも本山は京都市にあり、浄土真宗本願寺派は西本願寺、真言大谷派は東本願寺を本山としています。
浄土真宗本願寺派のことをお西、真言大谷派のことをお東と呼んだりもします。
基本となる教義は同じですが、葬儀の流れや作法に少し異なる部分があります。
(1)僧侶による読経
・帰三宝偈(きさんぽうげ)と路念仏(じねんぶつ)を唱える
・三奉請(さんぶじょう)を唱え、仏様を迎える
・正信偈(しょうしんげ)、念仏、和讃を唱える
(2)焼香
僧侶、遺族、親族、参列者の順に焼香をおこなう
(3)出棺・火葬
火葬前には重誓偈(じゅうせいげ)などの偈文(げもん)や念仏、回向(えこう)を唱える
(4)還骨勤行(かんこつごんぎょう)
収骨を行い、阿弥陀経、念仏、和讃、回向を唱え、最後に御文章(ごぶんしょう)を唱える
(1)僧侶による総礼(合掌)と読経
・勧衆偈(かんしゅうげ)、短念仏(十遍)、回向(えこう)、を唱える
・三匝鈴(さそうれい)という鈴を打ち鳴らし、路念仏、表白(ひょうびゃく)を唱える
・正信偈(しょうしんげ)、短念仏、和讃、回向を唱える
(2)僧侶、遺族、親族、参列者の順に焼香をおこなう
(3)出棺・火葬・還骨勤行(かんこつごんぎょう)
・出棺後は東本願寺派と同様の流れです。

浄土真宗の作法やマナーは、その教えから他の宗派とは少し異なる部分があります。
特徴的なものをご紹介します。
浄土真宗のお葬式で、他の宗派と特に違うマナーは「臨終即往生」の考え方からくる部分です。
「冥土をさまよう」という概念はなく、葬儀の時点ですでに故人は成仏し、仏様となっています。
だから、お悔やみの言葉でよく使われる「ご冥福をお祈りします」と言う言葉は当てはまらないのです。
浄土真宗の葬儀では「哀悼の意を表します」は「お悔やみ申し上げます」などがふさわしいです。
また、香典の表書きについても「御霊前」ではなく「御仏前」と書くようにしましょう。
浄土真宗では数珠の形も特徴的です。
仏教において数珠とは、唱えた念仏の数を数えるために用いられるものです。
浄土真宗では念仏を唱える回数を決めておらず、念仏を唱えることを必須としていないため、数珠は念仏の数を数える形にはなっていないと言われています。
正式数珠では男性用と女性用で形が違いますが、略式数珠を使用される方も多いです。
浄土真宗の焼香の作法は、つまんだお香を額に近づける動作(押しいただく)はありません。
お香をつまんだらそのまま香炉へくべ、合掌して「南無阿弥陀仏」を唱えましょう。
お香を香炉へくべる回数は本願寺派では1回、大谷派では2回です。
線香をあげる際には2つか3つに折り、立てずに寝かせてお供えします。
線香の本数は本願寺派では1本、大谷派では特に決まりはありません。
浄土真宗は厳格な儀礼や儀式も少ないため、家族葬など故人や遺族の想いを反映させた葬儀形式とも相性の良い宗派と言えるのではないでしょうか。
ウィズハウスで行われた、浄土真宗の葬式事例をご紹介します

本当に近しい7名の家族でのお見送り。
会場では思い出の写真をスライドショーで流し、毎日通われていた温泉のお写真とお風呂セットもご用意。
出棺時は「行ってらっしゃい!また会おうね」と拍手でのお見送りで、とてもアットホームな葬儀となりました。

花が大好きだった故人様。
祭壇はご家族のご希望により花いっぱいで豪華に、棺にはご趣味であったダンスの衣装を添えました。
ダンスの衣装はレースに散りばめられた虹色のビーズがキラキラと煌めき、故人様の明るい笑顔が偲ばれるとても華やかな葬儀となりました。
・「他力本願」の教えを説く浄土宗から生まれた浄土真宗。特別な戒律や修行を必要とせず、「浄土真宗を信じるだけで誰でも救いを得られる」という「絶対他力」の教えを説き、現在日本の仏教宗派の中で最も多くのお寺と信徒を抱える宗派です。
・浄土真宗はその中で大きく分けて本願寺は、大谷派の2つに分かれ、本山も別々となります。基本的な教えは同じですが、細かい作法や葬儀の流れが異なる部分もあるため、葬儀に参列する際はどちらの宗派なのかも気にしてみると良いかと思います。
・浄土真宗は「臨終即往生」という考え方で、葬儀の時点では故人の魂はすでに極楽浄土へ成仏しています。葬儀の中には戒や引導、追善供養の回向(えこう)といった、故人の魂が成仏するための儀式がないのも大きな特徴です。
・細かい戒律や宗教儀礼が少ない浄土真宗は、他の仏教宗派と少し異なる作法やマナーを持つのが特徴です。特に「冥土」の概念がないことから、「冥福」という言葉を使わない、香典袋には「御霊前」ではなく「御仏前」と書くという部分などは要注意です。
お葬式についてよくわかる
お葬式ガイドブックや各施設の紹介している
パンフレット、具体的な葬儀の流れがわかる資料など
備えておけば安心の資料をお送りいたします。
